|
人は何も食べなければ、飢えて死んでしまう。現在、地球上に生きる人間は、ほぼ全員がそう思っていることだろう。それは逆らいがたい自然の法則、原理であると。
しかし、古の時代より食べないで生きている人間が実は存在した。名もなきヨーガ行者、宗教家、無名の市井の人間。それは厳しい修行によってそうなった人と、たまたま、そういう資質を持っていてそうなった人と、二通りある。
何も食べない方が元気に生きられるという人々が、今現在、世界各地に、そして日本にも出現しつつある。彼らは、本当に食べていないのか。だとしたら、どうやってエネルギーを得ているのか。「不食」は、次代の人類の新たな有り様を示唆し、アセンション―次元上昇の目に見える具体例として現れ始めているのかもしれない―。
人は食べなくても生きられる―不食の実践者たち
 確かに、さほど遠くない過去に、食を絶って生を全うした人々がいた。たとえば、「コナースロイトの聖女」と呼ばれたドイツ人女性、テレーゼ・ノイマン。彼女は1962年に亡くなるまでの39年間、1日に聖餅(イエスの血と肉の象徴、硬貨大のウェハースのようなもの)1枚と、水を少し摂取するだけだったという。これを確認するため、1927年7月14日から2週間に渡って、24時間態勢で観察されたこともある。それでもやはり、彼女が聖餅と水以外のものを飲食した形跡はなかった。ノイマンは聖痕の持ち主としても知られる。毎週金曜日になると、彼女はイエスの受難を幻視し、その苦痛を自身の体に受けて、おびただしい血を流すのだ。 確かに、さほど遠くない過去に、食を絶って生を全うした人々がいた。たとえば、「コナースロイトの聖女」と呼ばれたドイツ人女性、テレーゼ・ノイマン。彼女は1962年に亡くなるまでの39年間、1日に聖餅(イエスの血と肉の象徴、硬貨大のウェハースのようなもの)1枚と、水を少し摂取するだけだったという。これを確認するため、1927年7月14日から2週間に渡って、24時間態勢で観察されたこともある。それでもやはり、彼女が聖餅と水以外のものを飲食した形跡はなかった。ノイマンは聖痕の持ち主としても知られる。毎週金曜日になると、彼女はイエスの受難を幻視し、その苦痛を自身の体に受けて、おびただしい血を流すのだ。
あるいは、インドの行者、ギリ・バラ。12歳4カ月から56年以上、不食を貫いたという。そうなったきっかけが、また興味深い。実は彼女はかなり食欲旺盛な子供だった。そのため12歳で結婚すると、3度の食事の度に姑から大食いを嘲笑されるようになった。
ある日、たまりかねて「もう死ぬまで食べ物に手を触れません」と、姑の前で宣言すると、一人になれる場所を探して天に祈った。
「主よ、どうか私に、食べ物でなく、あなたの光によって生きる方法をお遣わしください」
この直後、彼女はある僧侶の導きによってクリア・ヨガの一技法を習得し、食べなくても生きられるようになったのだ。この噂を聞きつけた富裕階級の人物が、3度に渡って彼女を自宅に招待し、各10日間ほど24時間態勢で見守った。それでも、彼女が何かを食べる様子は目撃されなかった。
日本では、明治期の霊能者、長南年恵が有名だ。元々小食だったというが、20歳の頃からは、生水とごく少量のサツマイモ以外、受けつけなくなった。長南は、霊能力を駆使して多くの人を助け、1907年、自分が予言した通りの日時にこの世を去った。
前述のような人々は、実在が確認されていても、心理的な距離はかなり遠い。そのため、いくら記録を読んでも、自分とは関係のない宗教的・超常的な世界で起こった出来事くらいにしか思えないのが誰しもの感覚だろう。ところが―。ここ10年ほどで状況が変化してきた。不食や小食に注目が集まり、実践者がじわじわと増えてきたのだ。
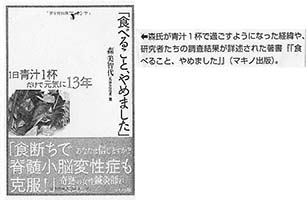 日本でのきっかけを作った一人が山田鷹夫氏だ。彼は2004年に、3年に及ぶ自身の不食体験をまとめた「不食 人は食べなくても生きられる」(三五舘)を上梓。その後もこのテーマを世に問い、不食という概念を広めた。 日本でのきっかけを作った一人が山田鷹夫氏だ。彼は2004年に、3年に及ぶ自身の不食体験をまとめた「不食 人は食べなくても生きられる」(三五舘)を上梓。その後もこのテーマを世に問い、不食という概念を広めた。
2010年には、白鳥哲氏の監督作品「不食の時代」が公開された。難病を克服する過程で1日に青汁1杯という生活に行き着いた森美智代氏の体験を核とするドキュメンタリーだ。
そして海外でも、不食の人々が次々と発見され、専門の医師たちやNASAなどによる研究が始まっている。彼らは一様に言う「食べない方が快適だから、そうしているのだ」と。こうした人々が表に現れてきたのは、何かの予兆なのだろうか。
*
 森美智代氏の1日1杯の青汁を飲むだけの生活は、すでに20年目を迎えている。森氏を不食に向かわせた最初のきっかけは、ひどい目まいとふらつきだった。脊髄小脳変性症という難病で、小脳や脊髄が次第に萎縮し、運動機能が失われていき、食い止める方法はない。若い時期に発症すると5〜10年で死に至るという。この時、森氏は憧れの職業だった養護教諭になって1年。いかにショックだったことか。その混乱が少し収まった頃、ある医師の顔が浮かんだ。断食や小食、生菜食などを組み合わせた「西田式健康法」によって、多くの難病患者を健康へと導いた故・甲田光雄医師だ。かつて森氏は、叔母と一緒に甲田医師が行う「健康合宿に参加し、1日2食、玄米お粥と豆腐を食べる「玄米小食」を体験したことがあった。 森美智代氏の1日1杯の青汁を飲むだけの生活は、すでに20年目を迎えている。森氏を不食に向かわせた最初のきっかけは、ひどい目まいとふらつきだった。脊髄小脳変性症という難病で、小脳や脊髄が次第に萎縮し、運動機能が失われていき、食い止める方法はない。若い時期に発症すると5〜10年で死に至るという。この時、森氏は憧れの職業だった養護教諭になって1年。いかにショックだったことか。その混乱が少し収まった頃、ある医師の顔が浮かんだ。断食や小食、生菜食などを組み合わせた「西田式健康法」によって、多くの難病患者を健康へと導いた故・甲田光雄医師だ。かつて森氏は、叔母と一緒に甲田医師が行う「健康合宿に参加し、1日2食、玄米お粥と豆腐を食べる「玄米小食」を体験したことがあった。
早速、甲田医院に行き、これまでの経緯を話して診察を受けると、甲田医師は言った。
「治るよ。お腹にガスが溜まっているのが原因。だから断食すれば治る」
この日から、養護教諭を続けながらの治療が始まった。甲田医院で断食をする。すると、その度に体が楽になり、目まいやふらつきが軽くなった。だが、断食を止めると、再び症状が悪化した。こうして2年ほど一進一退を繰り返していたものの、症状が次第に悪化し、仕事を辞めることを決意。すぐに甲田医院に入院し、腰を据えて断食療法に取り組み始めた。最初に行ったのは24日間の「すまし汁断食」。すまし汁を朝晩2回飲むほかは、水と柿の葉茶だけ。
 最初の長期断食から3カ月後には、2回目の断食を開始。その21日目に、森氏は自分が死ぬ夢を見た。甲田医師は、「気」が弱くなっている可能性ありということで、断食は打ち切りとなったが、森氏は、この夢は「再生」を暗示していたのではないかと言っている。 最初の長期断食から3カ月後には、2回目の断食を開始。その21日目に、森氏は自分が死ぬ夢を見た。甲田医師は、「気」が弱くなっている可能性ありということで、断食は打ち切りとなったが、森氏は、この夢は「再生」を暗示していたのではないかと言っている。
2回の長期断食を終えた森氏は、甲田医師の指導の下、玄米生菜食へと移行した。食事の内容は、数種類の生野菜をミキサーでドロドロにしたものと、3種類の根菜をそれぞれすりおろしたもの、生の玄米粉、塩。1日の摂取カロリーは、約900 カロリーだ。
最初のうちはともかく、日が経つにつれ、「いつまで我慢すればいいんだろう」という思いがよぎることもあったが、このころ価値観が変わるような体験をした。
その日は晴天だった。甲田医院の庭には野菜畑がある。そこに何気なく目をやると、ケールなどの葉野菜から、光り輝く美しいオーラが放たれているのが見えた。とはいえ、その時は自分の見ているものがオーラだとは気づかなかったそうだ。ただ、生き生きとした生命力が陽炎のように放射されているのを見て、「世の中には命がいっぱいあって、一緒に生きているんだ」という思いが溢れた。そして、野菜をいただくことは、その生命力をいただくことで、食事とは、命を生かすために、ほかの命をを移す営みだと気づいた。
この体験後、森氏は、何かを食べるという行為と、「おいしい」「楽しい」などの形容詞と結びつかなくなった。同時に玄米菜生食を自然に受入れられるようになった。
こうして玄米生菜食を開始してから一ヵ月半後には、甲田医院を退院。余命宣告を受けた体は、ほぼ発病前の健康な状態に戻っていた。
その玄米生菜食から質と量がさらに減って、とうとう青汁1杯になったのは、体重がどんどん増える、腹部が張るなどの変化が現れたからだ。森氏は、その度甲田医師に相談し、自分にとってベストな食事を模索した。その最終的な到達点が、青汁1杯だったのだ。
このような過程の中で、森氏の心身には様々な変化が起こった。まず、頭の中がクリアになった。短大時代に生菜食を体験した時点で、すでにその実感があったという。教科書を一度読むと内容が頭に入るので、試験は楽勝だったという。ニキビが多かった肌はスベスベになり、慢性頭痛や冷え性もなくなった。睡眠時間も減り、3〜4時間も眠れば十分とのことだ。森氏の不食にも「我慢」や「無理」がない。長い時間をかけて体と相談しながら実践していったもので、現在の形が一番自然なのだという。
それにしても―食べない人々の体内では、いったい何が起こっているのだろうか。
超小食者の腸内細菌は草食動物と同じ!?
「森さんの腸の中は、人間離れしている。まるで牛のようだ」
2000年に、森氏の腸内細菌について調べた生物学者・辧野義巳博士は、こう言って驚いたという。我々人間の腸には、確認されているだけでも500 種類以上の腸内細菌が棲息し、その数は100 兆個ともいわれている。これらの腸内細菌は、腸内で常に勢力争いをして
いる。そのパワーバランスには、元々個人差があるが、食事や環境などの要因でも「相」が変化していく。ただ、およその人は一定の範囲内に収まる。しかし、森氏の腸内細菌相は、明らかに異なっていた。通常なら人間の腸内にはほとんどいない細菌がいたり、特定の細菌が普通の何倍もいたりするのだ。
その代表的な例が、クロストリジウムという細菌だ。普通なら腸内細菌の0.1 %を占める程度なのに、森氏の腸には9.8 %も見られる。100 倍近い数字だ。クロストリジウムは、食物繊維を分解してエサにしながら、腸内にあるアンモニアからアミノ酸(タンパク質の構成要素)を作りだす。
食物繊維は、葉野菜や海藻などに多く含まれる成分だが、普通の人間には消化できない。その一方で、牛など草食動物は、食物繊維を消・吸収して、あの大きな体を維持している。それができるのは、クロストリジウムのような細菌を腸内に沢山すまわせているからだ。この点で、森氏の腸内は牛レベルなのだ。
また、人体内のアンモニアは、古い細胞を構成するタンパク質が分解され、エネルギーとして消費される(新陳代謝)際に、発生する。アンモニアのままでは有毒なので、尿素に変換された後、尿と一緒に排出される。だが、実はアンモニアには、タンパク質の材料となる窒素がかなり含まれている。クロストリジウムなどの細菌は、その窒素からアミノ酸を作りだす。いわば、捨てるはずの「カス」を再利用するのだ。このような細菌は、「アンモニア利用細菌」と称されるという。
辧野博士の調査によると、イモ類をはじめ、ほとんど植物性の食物しか食べないパプア・ニューギニアの人々の腸内にも、アンモニア再利用細菌が多く見られるという。
ただ、森氏の場合、生まれつきアンモニア利用細菌が多かったわけではない。断食や生菜食を継続的に行う中で、徐々に体が適応・変化していったのではないかと考えられる。
体を動かすエネルギー源は、ケトン体
森氏は、順天堂大学でも検査を受けた。その結果、栄養状態などは異常なしだったが、尿中に「ケトン体」が多く含まれていることが分かった。ケトン体とは、アセト酢酸、β―ヒドロキシ酪酸、アセトンの総称。脂肪酸やアミノ酸が体内で分解される時に生じ、エネルギー源として使われる。このケトン体が尿中に多いということは、体内にも多いということを意味する。おそらく森氏の体内では、ケトン体がエネルギー源になっているのだ。
普通の食生活を送っている人の場合、主なエネルギー源は糖質(ブドウ糖)である。
尿検査をしてもケトン体はほとんど検出されない。ここ数年、ダイエットやアンチエイジングなどに関連して、ケトン体が大きな注目を集め、関連書籍も出版されている。それらによると、ケトン体は優秀なエネルギー源のようだ。これをフルに活用すれば、太ることもなく、常に頭がさえ渡り、短時間の睡眠で満足でき、持久力も高まるという。
そのためには、ブドウ糖の元になる糖質を摂取しないことがポイントとなる。糖質を摂らなければ、ブドウ糖の血中濃度が低くなり、エネルギー源が不足する。それを補完するために、肝臓に蓄えられていたグリコーゲンからブドウ糖が生成される。だが、これは半日もたたずに尽きてしまうので、今度は筋肉のタンパク質からブドウ糖を作る。
これが切れると、ようやくケトン体回路のスイッチがオンとなる。肝臓でケトン体の生成が始まり、血中に供給される。これが細胞に取り込まれ、エネルギーに変換されていく。
なお、ケトン体から産出されたエネルギーは肝臓を除くほぼ全ての臓器と骨格筋で、エネルギーとして活用されることが分かっている。ちなみに、脳のエネルギーとなるのは、ケトン体の中でも、β―ヒドロキシ酪酸だ。興味深いことに、これが脳内に取り込まれると、α(アルファ)波の出現率が高まることが、東北大学の研究チームによって確認されている。
脳波がα波の状態になると、β―エンドルフィンという神経伝達物質が分泌される。
この物質は、幸福感の増大、脳の活性化、免疫力の向上等をもたらすといわれている。
 生菜食や小食を続ける人々の栄養摂取量が、肉や魚も食べる1日3食の一般人とかけ離れていることは間違いない。また、一般常識では、炭水化物、タンパク質、脂質が3大栄養素で、これに加えてカルシウムや鉄分などをバランスよく取ることが健康的だとされている。ところが、生菜食、小食実践者は、3大栄養素をほとんど取らないし、それ以外の栄養素も、推奨される基準値よりはるかに少ない。それでも貧血にならないし、骨量も十分だ。このことは、大阪教育大学教授・奥田豊子博士の20年以上にわたる追跡調査によって明らかにされている。 生菜食や小食を続ける人々の栄養摂取量が、肉や魚も食べる1日3食の一般人とかけ離れていることは間違いない。また、一般常識では、炭水化物、タンパク質、脂質が3大栄養素で、これに加えてカルシウムや鉄分などをバランスよく取ることが健康的だとされている。ところが、生菜食、小食実践者は、3大栄養素をほとんど取らないし、それ以外の栄養素も、推奨される基準値よりはるかに少ない。それでも貧血にならないし、骨量も十分だ。このことは、大阪教育大学教授・奥田豊子博士の20年以上にわたる追跡調査によって明らかにされている。
調査結果の一部を示す。4つの図中、○は菜食者(生菜食・小食実践者)、●は非菜食者を示す。また、森氏のデータは矢印を付した。
たとえば、図1を見ると、菜食者はエネルギーの摂取量が少ないが、握力は非菜食者と同じくらいだと分かる。また、図2を見ると、菜食者はタンパク質の摂取量が少ないが、血液中のアルブミン濃度は非菜食者とほぼ同じか、むしろ多い。
アルブミンとは、肝臓で合成されるタンパク質で、タンパク質の摂取量が少なければ、低下すると言われている。図3と4は、菜食者の骨量や血中ヘモグロビン濃度も、健康とされる基準値内にあることを示している。なお、奥田博士は、生菜食・小食実践者は、アンモニアから作られる尿素を再利用して、栄養源にしていることも突き止めている。
森氏の体内がどのような状況であるかは、こうして解明されつつあるが、なぜそうなっているかについては、未だ全く説明のつかない部分が多い―。
表紙にもどる |

