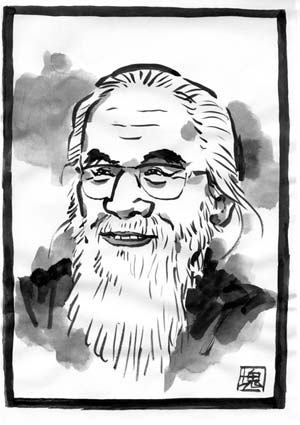番外編・追悼ナナオ論
ナナオ「カミガミ革命」はどうだ?
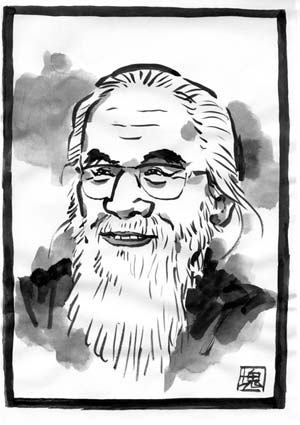
[「ヨガの達人」との出逢い]
「ぼくはヨガの達人でね」などとナナオが言うと、「またナナオ流のハッタリか」と私は苦々しく思ったものだ。
60年代半ばから70年代半ばまで、ビートニックからヒッピーの時代のほぼ10年間を、ナナオと活動を共にしてきた私は、ナナオが人前で逆立ちなどヨガのアサナ(体位法)をして見せるのは、単なるパフォーマンスでしかないこと、坐禅にしても2、30分が限界であり、インド哲学は生齧りであることなどを知っていたからだ。
しかし85歳になって足腰が衰えても、医者とも薬とも縁のない健康な体で、コロリと転んで「痛い!」と言ったかどうかはともかく、そのままあの世へ行ってしまったと聞いて、やっぱりナナオはヨガの達人だったのかと思った。
ナナオの死が2日後の朝日新聞(12.25)に報じられたのは意外だった。もっとも略歴などは全く記されていなかったが。ナナオは海外からは「日本で真のコスモポリタンな詩人」などと評価されているが、日本のマスコミを徹底的に拒否してきたから、新聞社にもTV局にもナナオに関する情報は一切無いのだ。
従ってナナオを知っている日本人といえば、祭や詩の朗読会などで直接ナナオと出逢った仲間か、カウンター・カルチュア系のミニコミの読者に限られている。
私にナナオを紹介してくれたのは、新宿ビート族という若者集団のボス的存在だったナーガである。東京オリンピックの翌65年春のことだ。当時私は新宿の街頭で似顔絵を描きながら、画家を志していたのだが、ビートニックに出逢ってから心が揺れ動いていた。
結局ナナオに出逢って間もなく、私は高円寺のアパートと全財産を放棄し、リックひとつでヒッチハイクの旅に出た。ドロップアウトである。そしてその夏、鹿児島でナナオとナーガと落ち合い、短パンスタイルの3人の野蛮人は奄美群島を2ヶ月間、無一文で旅をしたのである。それはハードな試練だったが、私は2人の先達からビートニックの旅を学び、南の島々とサンゴ礁の海のめくるめく生命力と解放感を味わった。それは諏訪之瀬島や奄美大島など、その後ほぼ20年間にわたる私のコミューン運動の原点となった。ナナオが42歳、ナーガが23歳、私が28歳の夏のことだ。
67年のサマーオブラヴに始まったヒッピーブームにより、私たちはマスコミの大攻勢を受けた。マスコミに対して無知、無防備だった私たちはメディアは使いようだと、ナナオの止めるのも聞かず、テレビに出演したり、週刊誌のインタビューの相手になった。結果的にブームは全国的に広がったが、ムーヴメントは風俗化し、毒抜きされた。
ナナオは終始一貫してマスコミを信じなかった。それは警察と同じように、我々を追いかけ、自由を侵害する権力の走狗だとして、その拒否反応は半端ではなかった。
[シモジモとカミガミ]
「部族」2年目の春、国分寺のコミューンがわが国初の大麻取締法によるガサ入れで、5名が逮捕された時、諏訪之瀬にいた私はすぐにでも救援に行きたかったのだが、ナナオから「警察やマスコミなどのシモジモとつき合っている暇などないはずだ」と諭されて、思い止まったのだ。
その時私はナナオが声をひそめて「シモジモ(下々)」と差別する対象が、警察官やマスコミ人種のみならず、彼らによって支えられている巨大な権力機構の頂点に向けられているのを知って、背筋がゾクッとした。
天皇や権力者を下々と呼ぶ逆差別意識は、相対的に自らを「カミガミ(上々)」とするエリート意識によって支えられているはずだ。ではナナオのエリート意識の根拠はどのへんにあるのだろうか。
戦時中、ナナオは予科練のレーダー係として、鹿児島の最前線基地に配属された。そこは決して殺されることのない安全地帯だった。彼は神風特攻隊の出陣を見送った夜、陸軍と海軍の情報合戦でせしめたウイスキーを呑んで、ひとりバッハを聴いて過ごしたとか。
戦後は東京の闇市世界をルンペンやニコヨンなどをして徘徊した後、『改造』という当時は『中央公論』と論壇を二分する総合雑誌の社長秘書に抜擢され、この国の知識階級のお粗末な内実を知り、日本に絶望し、亡国を予見したという。
社長の死による『改造』の廃刊を期に、国家体制をドロップアウトし、無住、無所有のビート詩人として唯我独尊の旅に出たきり、2度とシモジモの世界に帰ることはなかった。国家との関係は、パスポートの取得程度のものか。
戦中と戦後の2度にわたる情報最前線の経験によって、マスコミがいかに巧妙に国民を騙し、洗脳するかを知ったナナオは、選ばれた者の恍惚と不安のうちに「日本というのは天皇を中心にしたシモジモの国である」というパラダイム・シフトを体験したのである。
「カミガミ意識」を高め、世界を革命するためには、「シモジモの国家」に叛逆することではなく、自己を信じ、尊び、錬磨して、力強く、愉快に生きることだと悟った。それが犬死させられた同期の桜の無念に応えて、予科練の生き残りにできる唯一の供養でもあろうか。「友よ、おまえの代りに、金髪の女とも寝てやったぜ!」
60年代前半、ナーガなど若いビートニックが、自分たちの先達を新宿のカオスの中に発見した時、当のナナオは既に自らのライフスタイルから革命哲学までを確立させていた。それは亡国日本に替わる精神的、霊的な「カミガミの国」を用意すること。だから「自分の目の黒いうちに革命の実現を見ようと思うな」とナナオは言っていた。
仲間に対してナナオは厳しかった。ドロップアウトしながら都会の安易さに溺れ、旅をしない怠け者には「枝ぶりの良い樹があるよ」と言い、金がないと嘆く奴には「金は銀行にある」と言い、分別臭い奴には「17歳で死んじゃおう!」と言った。常に背筋を伸ばし、自己を律する姿は武芸者のようでもあった。
学問や仕事に励むことを否定はしなかったが「プロにはなるな」と注告した。プロになれば金になり、資本主義体制に組み込まれ、管理され、反革命化されてしまうだろう。永遠のアマチュアリズムこそ自由の条件だ。何事も浅く広くの雑学博士は、ヨガも然りだ。
「部族」のオープニング・セレモニーとなった67年春の新宿のイベントで、ナナオはミラレパの詩を意訳して、自らの決意表明ともいうべき詩を朗読した。
「私は乞食、まるはだか、無一文、生活とは関係ない ここに住みつく謂(いわれ)もない I am holy one of men」
このフレーズはビートニックには大きなショックだった。大地に帰り、生活に根づき、オルタナティヴな共同体を築くという「部族」のビジョンからすれば、ナナオの「永遠の旅人宣言」は明らかな矛盾だった。その矛盾が運動のテンションを高揚させた。コミューンは初期の開拓段階では生活共同体というより、修行道場アシュラマだった。メンバーの大半がまだ独身だったのだ。
諏訪之瀬島のバンヤン・アシュラマで、ナナオとは何回か星空のアシッド・パーティを共にしたものだ。火山の響き、潮騒、竹林のざわめき、虫たちの歌などをバックコーラスとして、ナナオと飛んだフリーソングの宇宙飛行は最高だった。私たちは「カミガミの国」で「神々意識」を満喫したのだった。しかしこの神々意識がナナオをとんでもない境地に導いたのだ。
[「半神」への造反]
ナナオが初めてアメリカを訪れたのは69年。仏教について質問されたナナオは「アイ・アム・ア・ブッダ」と答えて、カリフォルニア・ルネッサンスに一大センセーションを巻き起こしたという痛快な話を聞いた。
当時ヒッピーブームのカリフォルニヤでは、ヒンズー教、チベット密教、東南アジアの上座部仏教などの沢山のグルが教えを説いていたが、ブッダを名乗るグルはさすがに皆無だった。
ナナオは「東洋の神秘」とか「半神」などと、大いにもてはやされ、人気者になり、すっかり舞い上がってしまった。71年春、意気揚々と帰国したナナオを、東京で迎えたナーガは、私のいた諏訪之瀬へナナオと共にやってきた。そして久しぶりで3人だけになったある夜のこと、ナーガはナナオに対して「アメリカの若者にちやほやされたくらいで舞い上がるのはやめろよ、みっともなくてしょうがないぜ!」と、厳しい口調で諌(いさ)めたのである。
その時ナナオは返事もできないほど落ち込んだが、再びアメリカへ渡り、諏訪之瀬島の観光開発に対しては早々と73年に、ゲイリー・スナイダーやアレン・ギンズバーグなどと「ヤマハボイコット」の狼火を上げた。
75年に諏訪之瀬のコミューンが解体し、ナナオも参加した東京中心の「ヤマハボイコット運動」も終り、私は奄美大島の石油基地反対闘争の現地に、新しいコミューン「無我利道場」を築いた。そして2年目の夏、反対運動のための「枝手久祭」を小さな部落で催したのだが、沢山の帰省客と共に、数10人のヒッピー仲間が参加し、一触即発の緊張状態の中で、ナナオは毎晩のように大声でフリーソングを歌い、老人たちを不安がらせた。ナナオの自己中は今でいうKY状態だったのだ。
祭りが終わって、名瀬港にナナオを送り、出航までのひと時を、波止場で一杯やっていたところ、突然ナナオが言った。
「ポン 困ったことだ。日本の若者はだいぶ遅れているようだ。アメリカの若者はぼくのことを『半神』と呼んでいるが、日本の若者はまだ分かっちゃいない……」
私はナナオが冗談を言っているのかと思った。あるいは聞き違えかとも。しかしそうでないことが明らかになるにつれて、頭の中は真白になっていった。返す言葉もなかった。かつてのナーガの注告も馬耳東風だったのだ。やがて長い汽笛を残して、ナナオは私の心の中から去っていった。
しかしこれは私の心だけの問題ではなかった。「戦うコミューン無我利道場」を標榜する手前、ナナオの超人主義やグルイズムを批判しておく必要があった。そこで私はコミューンの機関誌に「ナナオは超人でも仏陀でもなく、我々と同じフリーク、ボヘミアン、単なるナルシシストだ」という意味のことを書いた。それがポンを最も信頼していたはずのナナオにとって、どれほど衝撃的な裏切りかを承知の上で。
それから4半世紀、25年間、ナナオと私は出逢いを避ける仲となり、例え出逢ってもほとんど口をきかなかった。それでも私の方から折れて出たことが何回かはあった。例えばバブル最盛期の「88いのちの祭り」に際しては、私からアメリカにいたナナオに参加を呼びかけたのだ。ナナオは祭りの前に帰国したが、場所がスキー場だという理由で参加を拒否した。本当の理由はポンが仕掛けたイベントだと知ったからだ。従ってその後、90年の大山、91年の六ヶ所村、2000年の鹿島槍など「いのちの祭り」は全てボイコットしている。また93年の「ほら貝25周年イベント」にも、姿を見せなかった。
[4半世紀ぶりの和解]
2000年秋、ゲイリー・スナイダーの来日イベントが東京湯島公会堂で開催されたが、どうせナナオが仕切っているはずなので、私は参加する気はなかった。ところが三省から是非との誘いがあり、ゲイリーにも会っておきたかったので、当時住んでいた岐阜から新幹線で、酸素吸入器を曳きながら出かけた。この時の出逢いでナナオとの関係はかなり好転した。
2003年1月、東京のアースガーデンが主催したナナオの80歳の記念イベントに、私はセヴンやキヨシと共に詩を朗読して前座を務めたほか、娘の宇摩も津軽三味線で祝った。
人生の最も活動的な4半世紀を、ナナオと離反してきたことを私は後悔していない。もしあの時点でナナオに同調し、ナナオをカリスマ視していたら、カウンター・カルチュア運動はカルト化し、ポンという個性はスポイルされ、ナナオの亜流、2級品、エピゴーネンになっていただろう。だからナナオのエリート意識に対する造反は不可避だったのだ。
「正反合」の運動法則からすれば、一緒に曳いていた対抗文化の網を、二手に別れて曳くことによって、左側の問口を拡げ、フリークスの運動をより多様化、活性化する結果になったと思う。
神々意識について、ナナオはもう「半神」とは言わなかった。彼は何事につけても自分のことだけではなく、アレン・ギンズバーグとゲイリー・スナイダーを並べて褒めることを忘れなかった。このトリオこそはカウンター・カルチュア史上に燦然と輝く三位一体、最高神格トリムルティなのである。
これについては拙著『トワイライト・フリークス』(91年ビレッジプレス刊)の中で、次のように記しておいた。
「ネット世代は、カウンター・カルチュア神話のトリムルティの存在を知り、この日本語ペラペラの無国籍風詩人を『半神』ならぬ『3分の1神』と認め、コンピューター神殿の玉座にインプットするだろう」
昨08年8月、国分寺のほら貝が創立40周年の閉店記念行事として、ナナオの詩の朗読会を催し、数10人の「同窓会」になった。夜半過ぎ、ナナオと私は席を立って、マスターのヒロのアパートに泊めてもらった。かつての頑強な足腰も衰え、ナナオはヒロのつれあいの勝子さんに支えられて歩いた。寝床に入ってもなぜか眠れず、枕を並べて2.3時間も話し合った。きのう今日のことは呆けていても、過去の記憶は驚くほど鮮明だった。
彼はもう神々意識を卒業していた。長い自己暗示から醒めたように、超人でも達人でもないオノレを自覚していた。寄る年波が呆けを募らせ、一人旅ができなくなり、この2、3年は大鹿村のボブとミドリ夫婦に衣食住の全てを世話になり、遠出の時はアキの車に頼った。夜中、便所に起きて自分の寝床が分からなくなり、夜陰を彷徨うナナオの姿を何回か見たことがある。ナナオの内なるエリート意識は消滅し、カミガミもシモジモも無くなり、そのためその言葉にはムリもムダもなかった。
そこで私は自分だけでなく、仲間たちにもナナオの話を聞かせたいと思った。ナナオは詩は書くが散文を書かないから、具体的事実は文章化されていない。戦中、戦後の情報最前線の話から、世界を股にかけて歩いてきたこの40年間の話まで、日本人の全く知らないことをナナオから聞き出し、記録しておくべきではないのか。
私は9月の「山水人」のイベントで、ナナオとの対談を主催者の祖牛に提案し、最終日に約2時間、サワ、ボブ、ポンを聞き手に、ナナオとの対談を催し、アマナクニがそれを収録した。
それから約3ヶ月後のある冬の朝、全てのカルマを果たし終えたナナオは、大いなる安らぎのうちに、転んだついでにあの世へ旅立った。アキからの電話でナナオの死を告げられた時、私は思わず叫んだ。
「お見事!」
いま、耳をすませば「ナナオのミラレパ」の最後のフレーズが聞こえてくる。
「いずれあの世で道のため、共に力を合わせよう!」
| ヒッピームーヴメント史・目次 | 表紙 |