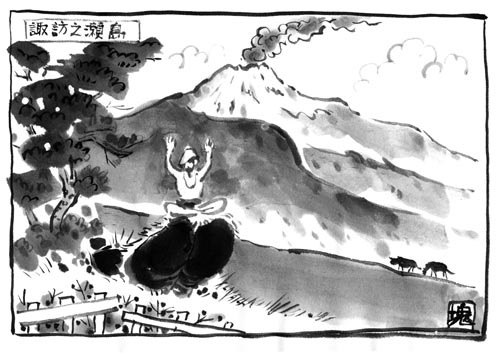第2章 コミューン運動「部族」の発足 1967
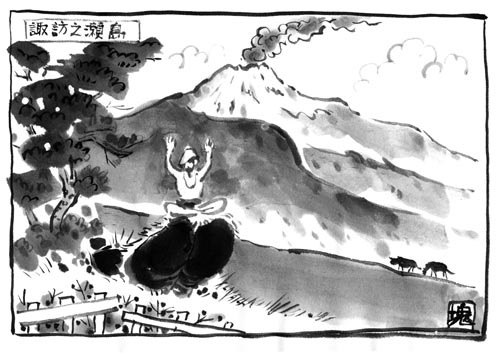
[信州富士見高原の雷赤鴉族]
中央線の終点高尾で下車し、リックを担いで駅を出ると、そこは甲州街道、国道20号線である。西へ向かってしばらく歩き、大垂水峠の手前でヒッチハイクをする。当時は車も少く、大型トラックが気易く止まってくれたものだ。
そこから約100キロ、甲州から急坂を登って信州に入ると富士見町だ。御射山郵便局前でトラックを降りて、国道左手の入笠山登山口を少し登るとけやきの巨木がある。江戸から一里ごとに植樹された一里塚である。そこで「ヤッホー!」と大声で叫べば、高原の彼方から返事が聞こえて、掘立小屋の中からヒゲまみれの男が姿を現すだろう。雷赤鴉族である。
標高1000メートル。振り返れば八ヶ岳の大パノラマ、そして富士見の名の通り、南東方向に富士山が聳える。神話なら山々の王者大山祇神の娘、岩長姫(八ヶ岳)と木花咲耶姫(富士山)の姉妹神を同時に拝めるスポットである。
時は5月、カッコウとホトトギスの歌声がからまつ林に鳴りひびく。私は1年間共同生活をした武蔵境のアパートを引き払い、炊事道具やふとん、それに100号のキャンバスなどを、雷赤鴉族の建設予定地に仮小屋を建ててキープしておいた。仮小屋は2、3人が横になれる程度のバラックで、「かたつむり」などと呼ばれていた。
「雷赤鴉族」の赤ガラスとは、中国の伝説にある太陽の中に住む使者のことだが、「部族」では大麻のことを「カラス」という隠語で呼んだ。雷は富士見高原の名物だった。
私は少年時以来、久々に鍬を握り、野菜の種を蒔き、山を歩いて薪を拾い、泉の水を汲んで飯を炊き、夜は満天の星の下で焼酎を呑んで数人の仲間とコミューンのビジョンを語り合った。
食料は国道まで降りて、農協のマーケットで買った。地元の人々は好意的で、私たちの実験に興味を持ち、いろいろ相談に乗ってくれた。近くの農家から仔山羊をもらったので、5月にちなんで「メイ」と名づけて飼うことにした。
まだヒッピーという名も、ブームも登場する以前だったが、4月のバム新宿フェスティバルを報道した『アサヒグラフ』は、雷赤鴉族の誕生間もなく、ライターとカメラマンが取材に入り、数日間滞在して共同生活をし、10ページ以上の特集を組んだ。カメラマンは中平卓馬、この男は終日かたつむりで寝ていたはずなのに、その鮮明な映像は40年を経た今も、私の脳裏に焼きついている。そこには若さと可能性の幻想が満ちていた。
ある日、私が1人でいたところ、東京からマモがラリーというアメリカン・ヒッピーを連れてきた。3人で八ヶ岳を仰いでカラスを回した後、ラリーが持参したカラスの種子を畑の片隅に蒔いた。これが吸うことを目的として、日本で栽培された最初の大麻である。
カラスが10数センチに育った梅雨明け直前に、私はオームたちに後を任せて、雷赤鴉族を出て南に向かった。
[諏訪之瀬島のがじゅまるの夢族]
「部族」が第2のコミューンに選んだ南海の活火山島諏訪之瀬に渡るには、鹿児島港から定期船「十島丸」に乗るしかない。当時250トンの第2十島丸は、鹿児島港からトカラ列島の島々を巡って奄美大島の名瀬港まで、週1回程度往復していたが、海が時化れば半月以上も欠航することもあった。
黒潮本流の真只中「魔の七島灘」に浮かぶ「天然の灯台」諏訪之瀬島と、「部族」との出会いはナナオに始まる。既に数人の仲間たちがこの神秘な島を訪れていたが、私にはこれが初めての訪問だった。
鹿児島では港の近くにある「十島会館」という村営の宿泊施設に、ナナオやナーガなど総勢10人近い仲間が集結し、買物や荷造りをした。「部族」結成に積極的に参加したゲイリー・スナイダーは許婚のマサと同伴していた。
十島丸は夕暮れに出航し、中之島などを経て、その夜は臥蛇島の沖合いで停泊した。70年代初めに無人島処分された臥蛇島だが、当時は断崖絶壁の上に数家族が住んでいた。オオミズナギドリの糞で真白になった沖の立神など忘れえぬ風景である。
翌日、800メートルの山頂から噴煙を上げる諏訪之瀬島に接近、サンゴ礁と切り立つ断崖に囲まれた海岸線は接岸できず、上陸は島民の出すはしけに頼った。岸辺では老人から子供までの全島民と、キャップなど先発隊の仲間数人が歓迎してくれた。
島民わずか数10名、10世帯が、車もテレビも商店もない絶海の孤島で、最後の縄文人と言っても過言ではないほど、文明に頼らずに生活していた。私たちは2つの集落から
更に1キロほど離れた山麓の牧場付近で荷を下ろした。この一帯の竹薮を切り拓いてコミューンを建設することを、島民と十島村役場(在鹿児島市)から承認されたのだ。
キャップが棟梁になって竹の家の建設にかかっていた。コミューンの名は亜熱帯植物がじゅまるの樹にちなんで「がじゅまるの夢族」としたが、後に「バンヤン・アシュラマ」になった。
快晴の一日、10数名全員で御岳(おたけ)山頂に登り、噴火口の上でゲイリー・スナイダーとマサの結婚式を挙げた。いかにもそれは「神話的現在」を彷彿とさせた。噴火口はシヴァ神の巨大な水煙管の火口を想わせ、そのセレモニーは1組の男女の結婚という次元を超えて、新たな精神の冒険と理想社会の実験に挑む者たちの禊の儀式でもあった。コミューンという理想社会を築くためには、純粋で普遍的な愛と慈悲が不可欠であり、そのためには全人類、全生類との一体感を体験しなければならない。
「全ては一なるものの多様な顕れである」理論はそれで十分だ。問題は合一体験である。しかし現代人は忙しすぎて修行をする暇がない。そこで登場したのが「LSD 25」というインスタント・サマディのドラッグだ。
私たちが実験したのは、麦角というカビの一種から採れるアルカロイドを使用したオーガニックなもので、ハーバード大学のティモシー・リアリィ教授から、ゲイリー・スナイダーを通して日本の仲間たちにプレゼントされたものだった。
ゲイリーのガイドで朝方、私たち男女4人はカプセル入りの緑の粉末状のLSD25を摂った。日の出の頃、鈴を転がすようなアカヒゲの歌声に誘われて、竹の家から牧場へ出ると、丘の上から原始の太陽がユラユラと燃えながら昇るのが見えた。牧場を埋め尽くしている牧草の1本1本が、山々を覆っている樹木の1本1本が、呼吸し、揺れ動き、笑っていた。それは痙攣的でシニカルな笑いではなく、全てを肯定する大らかな笑いだった。
牛も、虫ケラも、竹薮も、竹の家も、がじゅまるの樹も、火山の噴煙も、雲も全てが肯きながら、笑っていた。そして私は悟ったのだ。あらゆる笑いの背後にたった一つの笑いがあることを。その唯一の笑いの震源地から発するバイブレーションに共鳴して、全世界は笑いに満ちあふれるのだ。故に、宇宙の本質は笑いであり、肯定であり、愛と平和であると。
その日一日、私は牧場の岩の上に坐って、この推論と実感を深めた。アカショウビンの「ピッピルルルーン!」アオバトの「ポーポーヒポー!」という魔笛のような歌声も「全てよし!」と聞こえた。そしてこのような至福感を、例えドラッグによるインスタント体験にしろ、世界中の若者が共有しえたら、世界は甦るだろうと思った。
断っておくが、この当時LSDは日本はもとより、アメリカでもまだ禁止されていなかった。「サマー・オブ・ラヴ」と呼ばれたこの夏、全世界で何百万発ものLSDが大爆発して、ヒッピームーヴメントの幕が開いたのである。(アメリカは67年にLSDを禁止)
8月下旬に諏訪之瀬島を出た私は、宮崎での「バム・アカデミー第3回フェスティバル」の準備に加わった。宮崎在住の画家伊東旭氏や後藤章氏などが中心になって、20数名のバムが集った。例によって、宮崎神宮から県庁までをフラワーパレード。ポエム・リーディングの集会を催した後、一つ葉海岸でキャンプインを行った。地元の若者たちも参加し、焚火を囲んで踊り明かした。地方都市に初めてヒッピームーヴメントの火を点したのである。
[摘発された栽培大麻第1号]
秋風を肌に感じる頃、私はヒッチハイクで信州富士見高原に舞い戻った。2ヶ月ぶりの雷赤鴉族には見知らぬ若者ばかりが10人くらいいた。ほとんどがこの夏の「フーテン・ブーム」に乗せられて新宿へ行き、警察の狩りこみを逃れてやってきたとのこと。
私は真先にカラス畑へ行ってみた。ところが無いのだ、1本も。おまけに植物を引き抜いた跡と、その周辺におびただしい足跡があった。若者たちに尋ねたところ、数日前に地元諏訪署の警官数名が捜査令状を持ってやって来て、植物図鑑を見ながら片っ端から引き抜いて行ったとのこと。
まさか、こんなに早く警察が動き出すとは予想もしていなかったので、彼らがどの程度大麻を理解しているかを探ってみる気で、私は任意出頭に応じることにした。ところが諏訪署では「あんなゴミをいつまでも保管しておくわけにはいかんから、検察庁へ回した」と言われた。
そこで、その足で諏訪検察庁を訪れたところ、初老の検事長から丁寧に迎えられ、押収された大麻草約20本を見せられた。2メートル近くも成長したそれらは芳しい香りを発していた。驚いたことに検事長は「これは麻でしょう。こんな雑草を警察はなぜ摘発したのでしょう?」と問うのだった。
こんな調子だったのだ。67年秋までは、日本中の警察も検察も大麻取締法の存在すら知らなかったのだ。要するにこの法律は、日本の、日本人による、日本のための法律ではなかったということだ。そこで私はマッカーサーの命令で大麻取締法が制定されたこと、それは日本の伝統文化を廃絶し、日本をアメリカ化するための占領政策であることを説明したところ、検事長は自らの無知を恥じ、礼を言った。別れ際に玄関まで見送ってくれた検事長は最後に一言「我々もこれから勉強します」だと。
それにしても諏訪署をして雷赤鴉族を捜索させ、栽培中の大麻草を摘発させた背後には何があったのか。察するに、これはアメリカのベトナム反戦運動が、ヒッピーという新しい若者運動によって勢いづいているのを知った警察権力が、日本への波及を恐れて仕掛けた予防弾圧だったに違いない。
私たちバムが去った新宿では、その夏「フーテン・ブーム」なるものが演出され、マスコミの宣伝に乗せられた若者たちが家出して、新宿東口の緑地帯、通称グリーンハウスに集まり、睡眠薬を飲んでラリッているところを片っ端から警察に補導されたのである。しかし彼らは睡眠薬ハイミナールは持っていても、誰もマリファナは持っていなかった。かくて当局の「ヒッピー狩り」は収穫ゼロだった。
しかし警察は補導したフーテンたちから、信州富士見高原で、元新宿ビートたちがアジトを作っているという情報を得た。そのアジトでマリファナを栽培しているに違いないという警察庁の推理は見事に的中したのである。かくて栽培大麻を摘発したものの地方の警察や検察が、大麻取締法の存在すら知らない状態では事件にはならなかった。しかし「マリファナの尻尾」はつかまれ、警察権力の照準はピタリ「部族」に合わされたのである。
[新宿の葬式パフォーマンス]
「雷赤鴉族」「がじゅまるの夢族」に次いで、「部族」は東京国分寺に地下室付きの長屋を借りて「エメラルド色のそよ風族」という第3のコミューンを立ち上げた。その代表責任者である山尾三省は、雷赤鴉族の土地所有者として登記されていたことから、私は三省に「奴らは今から大麻のことを勉強すると言ってるぞ!」と警告しておいた。
日本製ヒッピーに探りを入れてきたのは警察権力だけではなかった。マスメディアはNHKが真先に動いた。「現代の映像シリーズ」の「ある青春の砦」は、雷赤鴉族とがじゅまるの夢族を取材し、共に働き、共に食い、共に座禅するまじめ若者集団を紹介して「ブゾクは建設的で夢がある」として、都会で睡眠薬にラリッているフーテンとの相違を明らかにした。ただし「ヒッピー」という言葉は使わなかった。
お陰で雷赤鴉族は地元の人たちから「からすさん」と呼ばれ、野菜や家具などの差入れがあり、稲刈りの手伝いにも行った。9月末にメインセンター「雷赤鴉聖殿」の建設に着手するまでは3、4軒の掘立小屋に分散して宿泊していたが、時には40人近くに膨れ上がり、食事も大変だった。
私はナーガとマモとでミニコミ作りを始めたので、東京と富士見を往復して「部族」の世話人を務めた。
その頃、元バムのアキタが墨染めの衣のまま禅寺をドロップアウトしてきた。「新宿はどうなってるか?」と問われて、私たちは半年間もごぶさたしている新宿が懐かしくなった。寝取られた女みたいな街だが、たまにはお礼参りのハプニングでも仕掛けてやろうかという話になった。
そこでアキタと共に、20数名のバムは、久々に新宿へ押しかけた。東口駅前のフーテンの新名所グリーンハウスの一画に祭壇を作り、中央に仲間のジャンが両脚を組んで両腕を広げ、舌べらを出してヨガのポーズをしている裸の写真に、黒いリボンを掛けて飾った。花や焼酎を添え、ローソクを点し、線香を焚き、坊さんのリードで全員が般若心経を高らかに唱えた。ラッシュアワーを避けたのだが、またたく間に野次馬が群がり、黒山の人だかりになった。交番のお巡りが飛んできて
「無届けデモだ、責任者は誰だ?」と怒鳴るので、すぐ横にいた私は静かに
「デモではありません、葬式です」と答えた。プロの坊さんが読経しているからパフォーマンスとは思わなかったのだ。お巡り達が3、4人集まって困惑していた。連中は私が責任者だと思ったらしく
「何とか早く止められないものですかね?」などと相談にくる。私はしんみりと答える。
「死んだ本人が、このグリーンハウスを限りなく愛していたもんですからね……」
「へえ こんなところをねえ?……」
彼らが何か言うたびに私は答えた。
「なにしろ葬式ですからね……」
するとお巡り達も言うのだ。
「そうですね、葬式ですからね……」
もう新宿東口はパニック状態だった。アキタは禅寺で覚えてきたお経を片っ端から唱えていた。太鼓や鉦やタンバリンまで用意していたから、ほとんどお祭り騒ぎだった。勿論、物事には限界というものがある。葬式にだってケジメはつける気だった。お巡り達がいっぱい出てきて交通整理をしていた。私たちはほとんど身動きできなかった。それでもジャンの写真を持ったアキタを先頭に、どうにか人垣を抜け出して、風月堂の通りに向かった。
無届デモもクソもなかった。こっちはただ歩いていただけなのに、金魚のフンのように野次馬がいっぱいついてきた。カメラマンが前や後ろを走り廻り、通行人が凍りついたように立ち止まっていたが、私たちはマントラを唱えながら、「やったぜ、ベービィ!!」という気分だった。
風月堂の前にさしかかると、ウエイトレスが飛び出してきて、ジャンの写真を見るや
「あら、この人ついこの間まで元気だったのに!」と言って合掌した。
その日一日、哀れなジャンは都内某所で軟禁状態になっていたことは言うまでもない。 ●