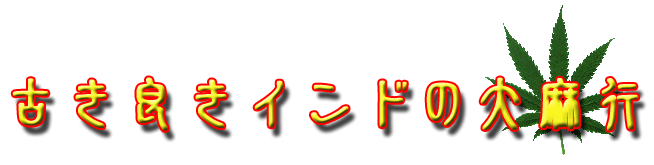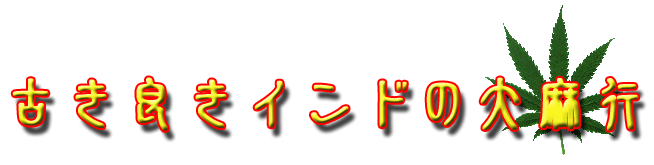第2部を開始するに当たって、タイトルの「古き良きインドの大麻文化」を、「古き良きインドの大麻行」に改題することをお断りします。やっぱり私は大麻の「文化人」というより、「修行者」なのですから。
最初のインドの旅から7ヶ月ぶりに帰国し、羽田空港のロビーで出迎えの群衆を見た時、私は日本人の画一均質化した様相にゾッとして、このままきびすを返してインドの多様性と混沌の中へ戻りたかった。
それなのに何故10年間もの長きに渡って日本に留まったのか。それについては『なまえのない新聞』150号(2008年9月発行)から連載予定の「ヒッピームーヴメント史 IN ヤポネシア」の中で、詳しく語るつもりですが、ここでは72年春から82年春までの10年間と、台湾、香港、タイでの3ヶ月について、あらましを語っておきたい。2度目のインドの旅のバックグラウンドとして。

[Aとの関係 72年]
帰国後、Aの静養のため東京五日市に2DKのアパートを借り、新婚夫婦のような甘い生活を始めたが、借金の返済と生活費のため、月の半分は出稼ぎで似顔絵を描いた。
しかし沖縄返還直後、ヤマハの諏訪之瀬島観光開発計画が勃発したので、年末にアパートを引き払い、私は島へ、Aはとりあえず実家へ帰ったが、そのまま潮が引くように心も去っていった。
[諏訪之瀬島の観光開発 73年]
それから1年、私はコミューンの仲間たちとヤマハ対策を検討したが、私たちには法的に争う根拠はなく、先住島民の部落会と対立しては孤島での生活は不可能だった。
結局コミューンを解体し、家族単位で部落会に加入することになり、ヤマハの工事を尻目に、74年正月、私は島を出た。
[ヤマハボイコット運動 74年]
インドへ行くつもりで東京へ出た私は「ほら貝」で、コミューン運動「部族」の夢破れた仲間たちに会い、インド行きを断念、「ヤマハボイコット運動」の火をつけた。楽器のヤマハに対抗して、フリーコンサートを催してヤマハの悪口を歌いまくった。この運動は「部族」の枠を越えて、カウンター・カルチュアの様々なグループを連動させた。
[琉球弧キャラバン 75年春]
トカラ列島諏訪之瀬島に連なる奄美、沖縄、八重山の島々を、私たちは2ヶ月かけてキャラバンし、沖縄返還に伴う内地大資本の琉球弧侵略のすさまじさに驚き、ヤマハの観光開発もその一環であることを知った。そして何処の島にも、この侵略と戦っている島民たちがいることを知った。
[奄美大島・枝手久島CTS計画 75年春]
奄美大島焼内湾に浮かぶ無人島枝手久のCTS(石油基地)計画は、内外奄美人の総決起となったが、地元宇検村は賛成派と反対派に分裂、反目し合っていた。
斗争3年目、私は枝手久島に砦を築くことを提案し、そのために台風の目のような地主部落のどまん中に家を借り、「無我利道場」というコミューン作りを始めた。
[父親になる 76年]
奄美入植を機に、私は15歳年下で2歳の娘のいるミオと結婚し、翌76年9月、自宅出産で女児が誕生。感動の翌朝、漁から帰った仲間たちの報告によれば、隣の徳之島に核再処理工場(MAT)計画が発覚したとのこと。まさに生と死のメッセージを同時に受け取ったのだ。
ミオとは2人目の娘が誕生したあと離婚したが、2人とも戦線を離脱するわけにはいかず、離婚後もコミューンで共に暮らした。
[漁業権斗争 76〜78年]
反CTS斗争が海を守る戦いである以上、漁業権の獲得は不可欠だった。泳げない私が「アブリ漁」という反対派による集団網漁に参加し、漁協の妨害にも関らず無我利仲間3名で漁業権裁判に勝利し、ついに漁業権を獲得して、反対派は漁業権放棄ぎりぎりの3分の1を死守した。
[実力阻止斗争 79年]
79年秋、海上保安庁の巡視船が、環境アセスメント作りの水質調査のため、焼内湾に侵入したのを、アブリ船団は実力で追い払い、枝手久斗争の勝利を決定づけた。
[徳之島・核燃料再処理工場計画 80〜81年]
80年代に入るや、農地開発の美名の下に大手企業によるMAT計画の基盤整備らしき工事が始まった。私たちは「反核キビ刈り祭り」を計画し、キビ畑の中に借りた一軒家を臨時コミューンとして、12月から4月まで常時2、30人、延べ100人を越す仲間を集め、農家のキビ刈りを手伝った。シーズン・オフと同時にコミューンは解体したが、10数人の仲間が徳之島各地に分散して住みつき、島民との交遊を通して、反核予防戦線を構築していった。
[海外への情宣 82年春]
「そうだ、海外へ、アジアへ、MAT計画の危機を知らせに行こう!」と、私は思いついた。用地決定は83年春だから、まだ1年あった。そこで2種類の英文ビラを用意した。
1つは徳之島の核再処理工場計画のもの、もう1つは「東アジア半日武装戦線の死刑重刑攻撃に反対する支援連」に作ってもらったもの。「反核」と「反日」の2種類の英文ビラは、アジア問題の情報センターからの紹介で、バンコクのある新聞社の女性記者あてに事前に郵送しておいた。
[中国文化圏の台湾と香港 82年春]
82年4月、私たちは那覇港から、台湾の基隆行きのフェリーに乗った。途中で寄港した石垣港で、顔見知りのフリークからガンジャをもらったので、船室で泡盛を飲みながら吸った。おかげですっかり酔っぱらい、相棒のシフラからさんざん文句を言われた。
翌朝の基隆では、情報センターから忠告されていた通り、税関の印刷物チェックは厳しかった。英文パンフなど持っていたら、中国のスパイ容疑でパクられていたかも。
今回の旅の道連れになったシフラは22歳。アクセサリーの街売りをしながら、無我利道場へやって来た時は、まだハタチ前の生意気盛りだった。私との年齢差23。ガキは相手にしないつもりだったが、キビ刈りシーズン中にくっついたのだ。
しかしすでに1年以上が経過し、風波が立ち始めていたのだが、台湾では基隆も台北も安宿はいずれも鏡張りのラヴホテルだったので、すっかり仲良しになってしまった。
私の希望では琉球弧から東南アジアに連なる「南方ルート」を、船で渡ってみたかった
のだが、旅行会社から「貧乏人は飛行機に乗れ」と言われたので、台湾から香港へ飛んだ。摩天楼の谷間を施回しながら下降するのはスリルがあったが、香港は狭苦しいところだった。ただし台湾も香港も夜は露天の食堂街が楽しかった。インドにはないチャイニーズ文化である。
[バンコクの御目玉 82年春]
バンコクへ着くや早速紹介されたタイ人女性記者に会ったところ、日本語ペラペラの彼女ピクンは「不用心もいいかげんにして!」と、頭から私を叱りつけるのだった。
聞くところによれば、彼女がある朝出勤したところ、デスクの上に「反核」と「反日」の英文ビラの束が、むき出しのまま置いてあったとか。日本の情報センターからは知らされていなかったが、タイでは最近、77年10月のタマサート大学虐殺事件以来、ジャングルへ逃げ込んで、タイ共産党の下に武装斗争をやっていた学生ゲリラ達が、5年ぶりに投降していたのだ。
タイ政府は寛大にも、国家に銃口を向けていた学生たちを無罪放免にしたのだが、その代わり日本並みのソフト管理体制が、ばっちり敷かれつつあったのだ。ピクンには当方の情報不足と認識の甘さを平に謝るしかなかった。
その頃タイ国境は、東はカンボジアに侵入したベトナム軍との一触即発状態がつづき、西北のゴールデン・トライアングルでは麻薬王クンサーが暴れ回り、南の4州はマレーシア共産党をバックに分権独立斗争を戦っていたのだ。私は改めて自分が「平和呆け」した日本人だと自覚した。奄美で実力阻止斗争を体験し、公安警察の目を意識するようになった私でさえ、アジアの緊張に欠けていたのだ。
ピクンは新聞記者の傍、裏通りに小さな服飾店を開いていた。日本へ出張するたびに銀座のファッションを仕入れて来て、学生アルバイトを雇って経営していたのだ。気前の良い彼女は私たちを日本料理店などで御馳走してくれた。離婚したばかりで30歳前後、私の娘と同じ年頃の娘がいた。
[日本の経済侵略]
バンコクの宿は最初は駅裏の安宿街にとったが、取締りが厳しくてガンジャが手に入らなかった。カオサン通りは安宿が何軒かある程度で、まだ商店街など無かった。それでも駅裏の売春窟臭さはなかったので、カオサンに移った。イラン革命のため帰国できなくなった留学生などのイラン人が20人くらい、私たちと同じ安宿で共同生活をしていた。英文ビラを渡すと熱心に読んでくれた。
10年前、初めてバンコクを訪れた時、味の素のバンコク支店周辺の路上に、味の素印のトラックが20台くらい駐車しているのを見て、度肝を抜かれたものだ。だが今回、味の素は経済侵略のはしりでしかなく、いまやタイ市場は車から電化製品、日用雑貨に至るまで、日本製品に完全に占拠されてしまっていた。モノだけではない。ヒトもまた破廉恥をきわめていた。
あるときバンコクの大通りを、日本のツーリストバスが2台通った。そのバスの正面のガラス窓にはある大都市の「市会議員一同様」という日本語の札が貼ってあった。そして市会議員一同は各々が隣にタイ人のコールガールをはべらせて、白昼堂々と高級ホテルへしけ込んで行ったのである。
東アジア反日武装戦線がわが国の経済侵略に対して、連続企業爆破斗争をやったのを、アジアの側から見れば、日本人の良心として評価するだろう。
英文ビラを活かそうと、マレーシアのペナンまで汽車で行った。途中の水田地帯はまだ機械化されず、ほとんどが水牛を使っていた。ペナン港では10年前に乗ったマドラス行きの貨客船を調べたところ、もうデッキには乗せず、キャビンは航空運賃並みだった。
消費者運動の事務所を訪ね、英文ビラを渡したところ、日本企業が進出している北部マレーシアの大工業団地クララジュールを案内され、その工業用水のためヘドロの海と化したクララ河の河口を見学した。水俣病の発生も間近と思わせる悲惨な現実が、日本の経済侵略に原因があることを知って暗澹たる気分になった。
[カラワン・バンドとの出会い]
マレーシアからバンコクに戻り、ピクンを訪ねたところ、タイの新聞に「日本赤軍2、3名潜入か?」という記事が載ったとか。まさか私たちのこととは思わなかったが、当分はバンコクをずらかった方が賢明だという彼女の計らいで、翌日マイクロバスの一行と東部へ向かった。そのバスに乗り合わせた10数人の中に、カラワン・バンドのメンバーがいて、到着したのはモンコンの実家だった。
私はもとより日本では、まだカラワン・バンドのことは全く知られていなかったが、彼らは70年代初めにボブ・ディランを研究し、学生バンドを組んでプロテストソングを歌っていた反体制運動の人気スターだった。77年10月、国家権力と右翼によるタマサート大学襲撃事件に遭過し、1000人もの学生と共にジャングルに逃げこみ、タイ共産党に迎えられ、武装ゲリラとしてジャングルからバンコクに向けて「人民の声放送」のテーマソングを歌ってきたのだった。
だが30年余もジャングルに潜伏してきた共産党首脳部にとって、敵は依然として封建地主だったが、今や地主たちの土地は日本やアメリカなどの多国籍企業のアグリビジネスに独占され、地主そのものはもはや敵ではなく被害者であることを、学生たちは知っていた。怨念で戦っている旧世代と、ボブ・ディランを知ったヒッピー世代の断絶は埋めようのないものだった。その分裂のタイミングを読んだタイ政府は、ジャングルの学生ゲリラに投降をすすめ、無罪放免を告げたのだった。全員が武器を捨てて5年ぶりにジャングルから出て来たのである。
タイ東部の田園地帯の農家に到着するや、リーダーのスラチャイが私に2種類の英文ビラを読んだことを告げた。私の頼みに応じてモンコンが、近所からガンジャを仕入れて来てくれたので、カラワンの連中とボン・シャンカールをやった。
その後、半月ばかりシフラと東北地方を巡ってバンコクに戻った頃には、もう赤軍の噂も消えていた。私たちは居候中のカラワンの又居候になって、酒もガンジャもありの待遇を受けたが、彼らはコンサートの準備と練習で忙しかった。そこでピクンが、彼女自身が離婚するまで住んでいたという持ち家を提供してくれた。台所から寝室まで、メード・イン・ジャパンの家財道具が揃っていた。
しかし旅費を使い果たしたので動きがとれなかった。そこでルンピニー公園にたむろしていたハタチ前後の2人の若者を客引きにして、街頭で似顔絵業をオープンした。アッという間に黒山の人だかりになり、やがてカメラマンや新聞記者までが取材に来た。タイには街頭似顔絵業などという職業はなかったのだ。当時のレート(1バーツ10円)で1人20バーツは、20年前の新宿の相場だった。
1日2、3時間で2、30人を描くとへとへとになった。なにしろ客が途切れないのだ。タイの金で1日数千円といえば相当の稼ぎだったが、その金で公園のワルガキ共と毎晩のように、ガンジャとウイスキーで宴会をやったので、金は貯まらなかった。
それでもコサムイには行ってみた。空港はまだ無かったから観光客も少なく、ヤシの葉陰でマジック・マッシュルームを採った。シフラとはいよいよ限界が近づいていた。なにしろレストランでは別々のテーブルにつくのだから。
6月下旬、タマサート大学でカラワン・バンドの復帰第1回コンサートが行われた。在校生が仕掛けたこのイベントは銃弾の跡も生々しい大学の大ホールを満員にして、テレビや映画のスターまで前座に出し、トリにカラワンを用意してあった。ところがプログラムが延々と遅れ、スラチャイがVサインをしてステージに躍り出て、観客が総立ちになったのは深夜に近かったが、その間席を立つ者は1人もいなかった。5年ぶりに民衆の前に姿を現したカラワン・バンドがこれほど圧倒的な支持を得ていることと、彼らの音楽の素晴らしさに私は心底驚いた。
タイに3ヶ月近く、そろそろ潮時だった。ピクンには世話になりっぱなしだった。1度彼女からタイに農業コミューンを作らないかという提案があった。彼女も自分の娘をコミューンで育てたいという。土地も資金もあり、奄美の仲間たちも呼び寄せたら良いし、ビザの件は何とでもなるという。MAT計画さえ無ければ乗りたい話だったが、残念ながら断るしかなかった。
シフラとは別れることに決めた。趣味のちがいは決定的だった。アクセサリー屋のハシゴなどつき合いきれるものではなかった。スラチャイが心配してくれたが、日本の仲間から送ってもらったカンパを半分に分けて、別行動をとることにした。その時になって、私はインドへ行こうと思った。運動を離れて、もう1度自分自身を見つめたいという気になったのだ。
|